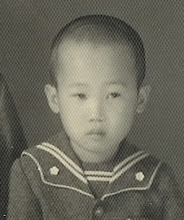物は使わないと失ってしまう(東西不用就會丟掉)
物は使わないと失なってしまう( 東西不用就會丟掉)
ある真冬の朝のこと,「おい,以前僕が着ていた厚い紺色のジャケットどこえいったの?」「知らないよ,もう長い間それを着ていないでしょ,自分でさがしてごらん。」これはかなり普通な出来事でしょう。長いこと使わない釣り竿,道具,着物・・・万が一,必要なときは家じゅうを捜索しても見つかりません。 僕の日本語はべつに達者ではありません。台湾生まれで,正式の日本教育は小学校三年足らず。第二次世界大戦の終り,僕は台湾で小学校の三年生でした。(当時台湾は日本の殖民地でした。)家庭環境か,自分が言葉に小賢しいせいか,日本語で会話することは,大人になってもかなり上手でした。しかし,読む事は難かしいかった,新聞,雑誌などは全く駄目だった。
台湾の大學を卒業してから、アメリカへ勉強にきました。ずうっと此処に住んでいて、三十年もあまり働いて,十年前アメリカで引退しました。引退後,暫らくの間,穏やかに暮らしていたが,矢張り何か面白い事でもするようにと思索していた。 丁度,こちらに二人の台湾の友達が日本語を習いたいと話し合っていた;コウさんとキョウさん。コウさんは農学博士,もう全引退で暮らしている,僕より年下六歳;キョウさんは脳科の医師,僕と十二歳の年下,又半引退(パートタイム)で頑張ています。僕もその時,日本語を勉強したい気持ちが徐々盛り上がっていたので,彼らにそれを教えてやることを約束しました。 十年前,此処に日本の領事館がいた,其処で日本語の教科書が貰えていた。僕は領事館から小学校一年から六年の国語教科書十二冊(毎年上下ニ冊),中学一年から三年の国語教科書合わせて五冊,ほかに中学一年で習っている地理と歴史の教科書各一冊を要求しました;かなり勇ましい格好で日本語を勉強するような志しでした。窓口に座っていた日本人の女性は疑わしく僕を見つめていた「こいつ,こんなたくさんな本を読めるかな,大切な日本教科書を無駄にしてくれないで。」と言う様な顔付きで。六十年ぶりで又日本語を勉強するその鮮やかさと嬉しさ,家に戻ってから僕はすぐにその貰って来た本のペ--ジをゆっくりとめぐり通した。ところどころに難しい言葉があるけれど,結構にコウさんとキョウさんに小学校六年生までの日本語を教えてやる事が出来ると想いました。彼らにこの思いを語って,それぞれ教科書を準備するようにと勧めました。準備が整えば,いつでも開始することが出来る。毎週一日,二時間僕の家でと言う予定でした。僕が彼らを教えるきっかけで日本語を習うと言うよりも,逆に言った方が相応しい;実は,日本語を一から勉強したかったので,ついでに彼らと一緒に学習しながら,単調な引退生活も一層豊かになれるのが楽しいかったのです。待ち兼ねて,僕はすぐに勉強を始めた,毎日少なくても二,三時間文章を繰り返して朗読しながら辞書の検索をしていた。一年生の文章は殆ど平仮名で書いていて,時には簡単な漢字「犬」,「空」,「男」,「女」などが現れてくる;此れ等の漢字は中国語でも意味が同じくつうじます。四年生で「テジナ」や「シバイ」と言う言葉は子供のときから知っていましたが,それが漢字で「手品」,「芝居」と書くのを見たとき,僕は呆れながら,勉強になりましたと嬉しかった;中国の言葉にはこんな漢字の意味が無いのです。コウさんとキョウさんの授業は二,三週隔てて始まりました,それは2004年の春頃の事でした。五年生に上がりますと,言葉もしだいに難しくなって来ました;「銀行へお金を預けに行く。」,「きじも鳴かずばうたれまい。」と言う諺,「母は,犬を飼うのを快く許した。」,「雨が強まり,水かさが増す。」...ですから,がんばって勉強しないと,"逆流で漕いで居る舟も後退するでしょう。",辞書検索の仕事も一層いそがしくなって来ました。六年生の教科書に「イ-ハト-ブの夢」と言う文章があった,作者は畑山博。それは宮沢賢治の生涯を描いた文章です。作者の解説では「イ-ハト-ブ」というのは宮沢賢治が想像で作った地名,それが彼氏の生まれ所、岩手県(イ-ワテ)によく似ていると語っている。作者はさらに,賢治が書いた数々の物語の出来事の舞台を地図上にまとめて,楽しい「イ-ワト-ブ」と言う全景地図を画いた。地図の形はもちろん岩手県の地図,中には銀河鉄道駅があって(銀河鉄道の夜),ほかに「イサドの町」とか「サンムトリ」とかと言う所の名前を変な読みにくい片仮名で示していた。
 |
| 僕の兄弟 |
台湾の大學を卒業してから、アメリカへ勉強にきました。ずうっと此処に住んでいて、三十年もあまり働いて,十年前アメリカで引退しました。引退後,暫らくの間,穏やかに暮らしていたが,矢張り何か面白い事でもするようにと思索していた。 丁度,こちらに二人の台湾の友達が日本語を習いたいと話し合っていた;コウさんとキョウさん。コウさんは農学博士,もう全引退で暮らしている,僕より年下六歳;キョウさんは脳科の医師,僕と十二歳の年下,又半引退(パートタイム)で頑張ています。僕もその時,日本語を勉強したい気持ちが徐々盛り上がっていたので,彼らにそれを教えてやることを約束しました。 十年前,此処に日本の領事館がいた,其処で日本語の教科書が貰えていた。僕は領事館から小学校一年から六年の国語教科書十二冊(毎年上下ニ冊),中学一年から三年の国語教科書合わせて五冊,ほかに中学一年で習っている地理と歴史の教科書各一冊を要求しました;かなり勇ましい格好で日本語を勉強するような志しでした。窓口に座っていた日本人の女性は疑わしく僕を見つめていた「こいつ,こんなたくさんな本を読めるかな,大切な日本教科書を無駄にしてくれないで。」と言う様な顔付きで。六十年ぶりで又日本語を勉強するその鮮やかさと嬉しさ,家に戻ってから僕はすぐにその貰って来た本のペ--ジをゆっくりとめぐり通した。ところどころに難しい言葉があるけれど,結構にコウさんとキョウさんに小学校六年生までの日本語を教えてやる事が出来ると想いました。彼らにこの思いを語って,それぞれ教科書を準備するようにと勧めました。準備が整えば,いつでも開始することが出来る。毎週一日,二時間僕の家でと言う予定でした。僕が彼らを教えるきっかけで日本語を習うと言うよりも,逆に言った方が相応しい;実は,日本語を一から勉強したかったので,ついでに彼らと一緒に学習しながら,単調な引退生活も一層豊かになれるのが楽しいかったのです。待ち兼ねて,僕はすぐに勉強を始めた,毎日少なくても二,三時間文章を繰り返して朗読しながら辞書の検索をしていた。一年生の文章は殆ど平仮名で書いていて,時には簡単な漢字「犬」,「空」,「男」,「女」などが現れてくる;此れ等の漢字は中国語でも意味が同じくつうじます。四年生で「テジナ」や「シバイ」と言う言葉は子供のときから知っていましたが,それが漢字で「手品」,「芝居」と書くのを見たとき,僕は呆れながら,勉強になりましたと嬉しかった;中国の言葉にはこんな漢字の意味が無いのです。コウさんとキョウさんの授業は二,三週隔てて始まりました,それは2004年の春頃の事でした。五年生に上がりますと,言葉もしだいに難しくなって来ました;「銀行へお金を預けに行く。」,「きじも鳴かずばうたれまい。」と言う諺,「母は,犬を飼うのを快く許した。」,「雨が強まり,水かさが増す。」...ですから,がんばって勉強しないと,"逆流で漕いで居る舟も後退するでしょう。",辞書検索の仕事も一層いそがしくなって来ました。六年生の教科書に「イ-ハト-ブの夢」と言う文章があった,作者は畑山博。それは宮沢賢治の生涯を描いた文章です。作者の解説では「イ-ハト-ブ」というのは宮沢賢治が想像で作った地名,それが彼氏の生まれ所、岩手県(イ-ワテ)によく似ていると語っている。作者はさらに,賢治が書いた数々の物語の出来事の舞台を地図上にまとめて,楽しい「イ-ワト-ブ」と言う全景地図を画いた。地図の形はもちろん岩手県の地図,中には銀河鉄道駅があって(銀河鉄道の夜),ほかに「イサドの町」とか「サンムトリ」とかと言う所の名前を変な読みにくい片仮名で示していた。
 |
| イーハトブ |
中学三年生は次の様な漢字を習うのです。「危篤の報せに急ぎ駆けつける。」,「血眼になって財布を捜す。」, 「厚顔無恥な人。」,「含蓄のある言葉を聞いた。」,「望みがかなって御満悦というところだ。」等等,これに僕の字引検索作業も更に忙しくなって来ます,努力して覚えた漢字も老年になってから記憶力が衰えているので,すぐに頭脳から消えてゆく。教科書のほかに初めて讀んだ本は,知り合いの人から貰った一冊の向田邦子(1929-1981)が著作なさった"眠る盃"です。これは凡そ五十題目の短篇を纏めて作った小冊です。文章はべつに難しくではなく,なめらかに書かれていて,著者の生活経験をユーモアな口調で描いている人情豊かな作品です。各題目をいくたび讀んでも飽きる事はないし,更に日本語の勉強に役たちます。話によりますと,彼女は台湾の上空で飛行機の事故で亡くなりました。実に悲しい残念なことです。では、此処で彼女の文章をひとつ鑑賞してみましょう。(父の風船)「いい年をして、いまだに宿題の夢を見る。"英語の単語を因数分解で解け"という問題に、汗びっしょりでベッドにはね起きたこともあった。私は、テレビやラジオの脚本を書いて御飯を頂いているのだが、時間ギリギリまで遊んでしまう自制心のなさは、小学校一年のときから少しも変わっていない。。。数学で、球形は沢山の楕円形から成り立っている。というようなことを習って、先生は例として紙風船を示していた。...そして、家へ帰って、ハタと当惑してしまったのである。当時はまだ、質のいい高性能接着剤はなかったから、ひょろ長い楕円形の端と端を張り合せて、紙風船をつくることは至難の業であった。あちらつければ、こちらがはがれる。遂に泣き出した私に、父は"もう寝ろ"とどなった。朝起きた私は、食卓の上に紙風船がのっているのを発見した。いびつで、ドタッとした、何とも不様な紙風船であった。...そして、この二月。父は突然六十四年の生涯を閉じた。死因は心不全。五分と苦しまず、せっかちな父らしい最期であった。...」次に讀んだ本は芥川龍之介(1892-1927)の名作「羅生門」,「藪の中」と「鼻」。龍之介の著作は読めば讀むほど,好きになりましたので,遂に「羅生門」の中にある一段を空覚えしました。「申の刻下りからふり出した雨は,未だに上るけしきがない。そこで,下人は,何を措いても差し当たり明日の暮らしをどうにかしようとしてーーいわばどうにもならない事を,どうにかしようとして,とりとめもない考えをたどりながら,さっきから朱雀大路にふる雨の音を,聞くともなく聞いていたのである。」これは,好きで繰り返して讀む中に空覚えをしたのです。小説の「藪の中」と「羅生門」を組み合わせて,映画「羅生門」が黒澤明(1910ー1998)の監督で作られた。「藪の中」からの一説の物語を鑑賞してみましょう。「多襄丸(三船敏郎)の白状」: 「あの男を殺したのはわたしです。しかし女は殺しはしません。...わたしはあの女の顔が,女菩薩のように見えたのです。わたしはその咄嗟の間に,たとい男は殺しても,女は奪おうと決心しました。...しかし男を殺さずとも,女を奪う事が出来れば,別に不足はない訳です。...そこでわたしは山のなかへ,あの夫婦をつれこむ工夫をしました。これも造作はありません。...山の陰の藪の中へ・・・」これで,僕もずいぶん日本語の勉強をしました。コウさんとキョウさんも真面目に,雨にも雪にも拘らず,毎週僕の家へ授業に来ました。彼らは,毎年ニ三回台湾へ帰って親孝行を尽くしますので,誰かのひとりが留守になった時には,"営業休み"の看板が我ケ家に現れる。あれこれ,彼らが六年生の教科書を終ったのは2011年の春でした。凡そ,七年間僕達が一緒に日本語を勉強したのです。日本語とかかわれば,此処にいるもう一人の台湾人を紹介しましょう。ヨウさんと言う僕よりも十二歳年嵩のオジサンです。戦争の終り,彼は台湾で大學を勉強していた。文学の嗜みがたかい,筆まめのオジサンです;漢文と日本語はおろか,英語で書いた散文詩も小冊で発行されている。僕は時折,面白い言葉を覚えると彼と語りあったり,繰り返しで読んでもわかり難い言葉があれば,彼から教えて貰いました。外国語を習うのは容易い事ではない。希望が叶うなら,その外国へ少なくても二三年住むことが出来れば,或いは,ここに住んで居ても,その外国の言葉を話す人達と交わることが出来れば,言葉の学習に大きな助かりとなります。僕達にはいずれもなかった。唯,本を読んで,僕はほかにもパソコンを使って日本のニュースを聞きながら,画面の文字を読んで勉強をしていた。...兎も角,皆も七年間ねっしんに勉強なさった日本語,自分で継続して勉強しなければ直ぐに忘れて行くと心に覚えて,コウさんとキョウさんに何時でも励まし合っています。(2012・7・24)

.mht!http%3ahttps://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsTRfzjh6Ymy14OMCC3awtpLMZSKSPVcS8rwsmSZuzF2CopeXOSXHeRh1IRCyucxK7wUvkG4MNA7UakPDdeX2UQvdmBONi5n87kqzVI2M8-elWijeEfkN7jjB7PNUkHL80yEhfQspts18/s220/chris.jpg)
.mht!http://buttons.blogger.com/bloggerbutton1.gif)